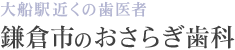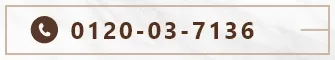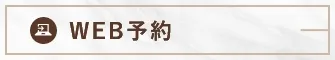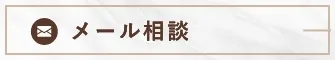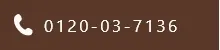歯周病とは

歯周病とは、歯垢に潜む歯周病菌が歯を支えている歯周組織を少しずつ破壊していく病気です。初期の自覚症状はほとんどありませんが、進行すると顎の骨が溶けていき、歯が自然と抜けてしまうことがあります。歯周病は気がつかないうちに重症化し、歯を失ってしまう怖さがあります。
歯周病とは、歯垢に潜む歯周病菌が歯を支えている歯周組織を少しずつ破壊していく病気です。初期の自覚症状はほとんどありませんが、進行すると顎の骨が溶けていき、歯が自然と抜けてしまうことがあります。歯周病は気がつかないうちに重症化し、歯を失ってしまう怖さがあります。
こんな症状はありませんか?
- ・歯ぐきが赤く腫れている
- ・歯磨きで歯ぐきから血が出ることがある
- ・口臭が気になる
- ・朝起きると口の中がネバネバしている
- ・歯ぐきに膿が溜まっている
- ・歯と歯の間に隙間ができて、食べ物が詰まりやすい
- ・歯がグラグラする
歯周病の原因
歯周病の主な原因は、歯の表面に付着した歯垢(プラーク)の中に潜んでいる歯周病菌によるものです。歯垢が蓄積していくと歯周ポケットは次第に深くなり、歯周病菌が歯の周囲に炎症を起こしはじめます。炎症を放っておくと進行して顎の骨が溶け、最終的には大切な歯が抜け落ちてしまうことになります。
また、歯周病はストレスや疲労、加齢、糖尿病などの持病、乱れた食生活、喫煙などの習慣にも深い関わりがあります。
歯周病がもたらす悪影響
近年、歯周病が全身に与える影響や、別の症状が歯周病に与える影響について研究が進められています。次のようなさまざまな症状が、歯周病と関連があるといわれています。
糖尿病
昔から糖尿病患者に歯周病の発症リスクが高いことは知られており、歯周病は糖尿病の合併症の一つといわれてきました。糖尿病によって高血糖が続くと、毛細血管がもろくなったり白血球の機能が低下したりして、細菌に感染しやすくなります。唾液分泌量が減って口の中が乾くことも細菌が増殖しやすい要因となり、歯周病の発症率が上がると考えられています。
また、歯周病の人は、歯周病ではない人と比べて糖尿病を進行させるリスクが高いともいわれています。
狭心症・心筋梗塞(虚血性心疾患)
歯周病の人は、心疾患を発症するリスクが高いといわれています。歯周病の細菌や歯周炎の炎症物質が、冠動脈に影響を与えることが考えられます。
誤嚥性肺炎
病気や加齢によって生理的機能が衰えると、誤って食べものや唾液が気管に入ることがあり、唾液中の歯周病菌などの細菌が肺炎を引き起こす場合があります。
早期低体重児出産
歯周病の妊婦さんは、低体重児出産や早産の確率が高いといわれています。歯周病による炎症物質が、へその緒を通じて胎児に悪影響を与えることも考えられています。
骨粗鬆症
閉経した女性はホルモンバランスが崩れることから、骨粗鬆症の発症率が高くなります。歯周病を発症した場合、骨粗鬆症の人は骨がもろくなっているため、その進行が加速されるリスクがあると考えられています。
歯周病の予防が生活習慣病の予防に
歯周病が全身に悪影響をもたらすということは、裏を返せば、歯周病を改善すればほかの症状にも良い影響があるといえるのではないでしょうか。歯周病を悪化させ、炎症反応を促す炎症性サイトカインは、歯周病を治療して病原性細菌を取り除けば産出が抑えられます。その結果、血糖値を下げるインスリンの働きが正常に戻り、血糖コントロールが改善されることになります。
毎日の食生活を含めた生活習慣を見直し、歯周病を治療・予防することは、生活習慣病の予防につながり、健康な人生を支えてくれるのです。
歯周病の進行状況
歯肉炎
歯ぐきが炎症を起こしています。まだ歯垢(プラーク)が石灰化した歯石は形成されておらず、顎の骨も溶けていません。歯磨きなどで出血することがあります。
軽度歯周炎~中等度歯周炎
プラークが石灰化した歯石が形成され、歯ぐきの腫れがひどくなります。歯ぐきが歯根から剥離し、歯ぐきが腫れることで歯と歯ぐきの間の溝(歯肉溝)が深くなって、歯周ポケットが形成されます。ポケットの深さで進行度が判断できるので、歯科医院で検査を受けましょう。顎の骨が溶けはじめるため、歯がグラつくこともあります。
重度歯周炎
顎の骨が大量に溶け、歯周ポケットがさらに深くなります。歯ぐきに膿が溜まり、口臭が悪化。この段階になると痛みを感じることもあり、抜歯が必要になることもあります。
治療方法
[軽度~中等度の歯周病治療]
歯周病は早期発見・早期治療が肝心です。初期段階で歯周病を発見できれば、治療も簡単に済みます。
PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)
患者さまご自身では落としきれない歯の汚れを、歯科医や歯科衛生士が専用の機器を使ってきれいにクリーニングする処置です。専用の研磨剤によって徹底的に歯垢(プラーク)を除去します。最後にフッ素塗布による歯をコーティングし、治療は1時間ほどで完了します。
デメリット
- ・保険適用外である
自費診療になりますので、保険の適用外になります。 - ・汚れが多いと時間がかかる
1本1本の歯を医師や歯科衛生士が丁寧に磨いていくため、汚れがひどい場合はお時間を要する場合がございます。行う前にカウンセリング等を行いますので、まずはご相談下さい。
費用
- ¥5,000~¥10,000(税込)
レーザー治療
レーザーを照射することで、歯周病の原因となる細菌を減らします。痛みはほとんどなく、外科手術に比べて治療期間が短いことが大きな利点です。当院ではCO2レーザーを歯周病の炎症を和らげる治療に導入しています。
デメリット
- ・歯を正確に切削することが難しい点が挙げられます。
- ・使用用途としては、虫歯の初期症状の際に限られます。
費用
- ¥3,000~¥15,000(税込)
スケーリング
プラークや石灰化した歯石を、スケーラーという専用の器具で取り除きます。
ルートプレーニング
歯周ポケット内部に付着したプラークや歯石を取り除き、歯の表面を滑らかに仕上げて付着を防ぎます。
フラップ手術
スケーリングやルートプレーニングでも症状が改善しない場合、部分麻酔をして歯肉を切開し、目視で確認しながらプラークや歯石を取り除きます。
咬合調整
咬み合わせの乱れによって咬む力が歯に偏ってかかると、歯周病の進行を早めることがあります。咬み合わせを調整することで、咬む際に歯にかかる力のバランスを整え、症状の改善を図ります。
連結固定
グラつきのある歯を健康な歯に固定して安定させる治療法です。
[重度の歯周病治療]
歯周病を放置しておくと症状は悪化し、細菌が歯を支えている顎の骨まで破壊してしまいます。歯がグラグラしたり、歯ぐきが黒ずんだり、膿が溜まって歯磨きで激痛が走るようになります。
重度の歯周病治療(歯周外科)に対応できる歯科医院は多くありませんが、当院では重度の歯周病の方に向けた歯周外科にも対応しています。
GTR法(guided tissue regeneration)
「組織再生誘導法」とも呼ばれる歯周外科治療です。
歯周組織の再生にあたって、歯肉が顎の骨の再生を邪魔してしまうことがあります。歯肉の再生は顎の骨の再生よりも速いため、顎の骨が再生すべき箇所に先に再生した歯肉が入り込んでしまうからです。これを防ぐため、「メンブレン(膜)」を歯肉と顎の骨の境界に挿入し、顎の骨の再生を促します。
エムドゲイン法
「エムドゲインゲル」とは、ブタの歯胚から抽出した骨を再生させる物質です。顎の骨を再生させたい部分に、この物質を注入する歯周病の外科的治療です。エムドゲインはGTR法におけるメンブレンと同様、先に再生してくる歯肉が骨の再生部分に入り込こむのを防ぐ働きをします。
[歯を失ってしまったら]
重度の歯周病で歯を失ってしまった場合、できるだけ早く補う必要があります。当院では補綴治療として、「インプラント」「義歯(入れ歯)」「ブリッジ」の3つの方法をご提案しています。
インプラント
チタン製の人工歯根を顎の骨に埋め込み、しっかりと結合させてから人工歯を被せる治療です。顎の骨と人工歯根が完全に結合するため、天然歯と同じような安定した咬み心地が得られます。
>> インプラントに関する詳細はこちらへ
義歯(入れ歯)
歯を失った場合、最も普及している補綴治療です。手軽に取り外しができるメリットがある一方、金具や「入れ歯」の境目が目立ちやすく、咬み心地が良くないというデメリットがあります。
ブリッジ
抜けてしまった歯の両側にある残った歯を削って人工歯をかぶせ、抜けた部分を補う治療です。橋をかけることに似ていることから、ブリッジと呼ばれます。健康な歯を削らなければならず、失われた歯の部分の顎の骨が痩せていくというデメリットがあります。
治療の流れ
①歯ぐきの検査
適切な歯周病治療を行うためには、検査をして歯周病がどの程度進行しているか確認することが重要です。
歯と歯ぐきの状態をチェックした後、歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の溝)の深さを測り、歯周病の程度を調べます。
レントゲンを撮って、歯を支えている顎の骨の状態などを見ていきます。
歯磨きの重要性をご説明し、正しい歯磨き方法の指導をいたします。
②検査後1カ月間
歯石の除去を定期的に行い、歯ぐきの状態を改善していきます。
歯磨きに問題がないか、チェックさせていただきます。
初診から1カ月が経過した時点で、再度検査を行います。
③状態の確認と治療計画
正常な状態が回復できたかどうかチェックをします。
改善した場合は、メンテナンスに移行します。
改善が見られない場合は、治療計画を立てて本格的な治療を始めます。治療が終了した時点で再度検査を行い、状態を確認します。
④メンテナンス
治療によって状態が回復しても、歯周病は再発する可能性があります。
ご自宅で正しい歯磨きを続け、定期的なメンテナンスを受けることで健康な状態を維持していきましょう。
歯周病にならないためには
定期的なメンテナンスと正しい歯磨きで、健康的なお口に
歯周病を予防するためには「プラークコントロール(歯垢の除去)」が欠かせません。当院では「定期的なメンテナンス」によって歯垢を除去するだけでなく、患者さまの口腔内環境に合わせた正しい「歯磨き」や、「食生活の改善」についても丁寧に指導していきます。
歯磨き
正しい歯磨きは、プラークコントロールの基本です。口腔内の環境は一人ひとり違うので、自分に合った歯磨きをしなければ、効率の良いプラークコントロールはできません。当院では、歯科医や歯科衛生士による歯磨き指導を行っております。
よく咬んで食べる
唾液は細菌を洗い流してくれるため、プラークコントロールにも効果があります。よく咬んで食べることによって歯周組織が鍛えられ、唾液の分泌量も多くなります。
生活習慣の改善
糖分はプラークをつくる細菌の大好物です。糖分の摂取を抑え、栄養バランスのとれた食事を心掛けましょう。ストレスを溜め込まず、規則正しい睡眠をとり、生活習慣を改善することもプラークコントロールのために大切です。
定期的なメンテナンス
どんなに時間をかけて正しい歯磨き続けても、ご自身だけでは十分なプラークコントロールはできません。定期的に歯科医院でのプロフェッショナルケアを受けることが大切です。通院を習慣化することで深刻な状況になること予防し、健康なお口を長く保っていくことができます。歯周病が気になる方は、当院までお気軽にご相談ください。
Q&A
歯周病
- 歯周病で骨がなくなってしまった場合、元に戻らないのでしょうか?
- 現在は骨の再生が可能になっています。ですが、現在の医療技術でも失ったものを元通りにするのは難しいため、できるだけ失わないように努めることが大切です。
- 自分が歯周病なのか、セルフチェックする方法はありますか?
- 歯周病であるかどうかは線引きが難しいです。
「口臭が気になる」、「歯ぐきが腫れている」などの症状がある際は歯周病の可能性がありますので受診をおすすめします。
- 歯周病と言われましたが、痛みがない場合は治療しなくてもいいですか?
- 歯周病はひどくなるまで痛みや自覚症状が出ないことも多いため、気付かずに生活している方が多くいます。
放置で自然治癒することはないので、長くご自身の歯を長く保つためにも早めの受診をおすすめします。
- 喫煙は歯周病に関係がありますか?
- ニコチンにより血行が悪くなることで、歯ぐきに酸素や栄養素が届かない、唾液の分泌量が減り、プラークや歯石が付きやすくなる、などといった原因からリスクは高いと言えます。
- 歯石は歯周病の原因になりますか?
- 直接原因にはなりませんが、歯石の間に細菌が入り込み、それにより歯周病を引き起こす可能性があります。
歯石は歯磨きでは取り切れないものが多くありますので、定期的なメンテナンスをおすすめします。